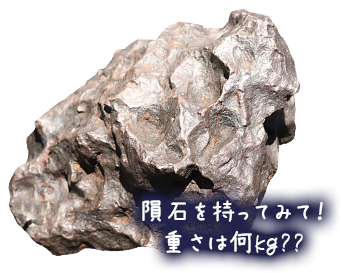山梨の研磨宝飾産業の歴史
現在は昇仙峡一帯での水晶の採掘は禁止されておりますが、今でもなお、水晶研磨と貴金属工芸の技術は発展の一途をたどっています。山梨でなぜ、宝飾産業が盛んにおこなわれるようになったのか、世界でもトップレベルの宝飾研磨技術を有する理由について山梨の宝飾産業の歴史をご案内いたします。
01.水晶と御岳昇仙峡
日本では、山梨県 昇仙峡での水晶産出が有名です。県北部、甲府市近郊の金峰山一帯には、かつて古くは武田信玄の治世の金山に端を発するという幾つもの鉱山が存在し、明治に入り近代化が行われた後には工学ガラスなどの資源として盛んに採掘されました。現在、稼動している鉱山はありませんが、牧丘町に位置する乙女鉱山では、産業遺産としての保存・活用への道が検討されています。
03.乙女鉱山での水晶産出
乙女鉱山は明治初頭から昭和50年代まで約110年間もの長い間山梨の宝飾産業を支えた水晶を産出した鉱山です。透明度の高い無色水晶・白色水晶を数多く産出したことで有名です。乙女鉱山の名前の由来は、最盛期の明治時代に若い男性は坑内で鉱石を掘り、年老いた女性は鉱石の選別、そして若い女性は鉱石を運ぶという男の鉱夫に混じり若い乙女が鉱石の運搬を務めたことに由来するといわれています。金峰山一帯で最も大規模な鉱山で、明治政府の水晶山開発推奨政策で盛んに採掘されるようになりましたが、第二次世界大戦後採掘量が減少し、昭和56年に鉱山会社が倒産し閉山されました。
04.水晶研磨の始まり
最初の加工品は縄文石器時代の「石やじり」であったといわれています。当時、「やじり」のほとんどは「黒曜石」とよばれる石で作られたものでした。しかし山梨県では水晶がたくさんとれたので、やじりに水晶を用いたのです。その後水晶は、自然の形のまま床の間などの置物することが主流でしたが、これを研磨し玉造り(水晶玉等への加工)する技術を教えたのは京都の玉屋弥助でした。江戸時代、天保5年(1834年)その頃、水晶の採掘は禁止されており、水晶を手に入れるためには雨などで自然に水晶が露出するのを待たなければいけませんでした。弥助は必要な水晶が得られるまでの待ち時間に金桜神社の神官たちに水晶の磨き方を教えます。これは、まだ山梨に研磨技術がなかった時代です。弥助は包丁や鰍の刃先などあり合わせの道具を用いて磨いたそうです。その次に水晶の買付にきた際には、研磨剤である金剛砂を持参し、本格的に水晶の磨き方を教えたといわれています。現在、この金桜神社には金峰山の水晶を京都の玉造りに加工させたと伝えられる「火の玉」「水の玉」の銘玉が昇仙峡の金桜神社の御神宝として、今も大切に納められています。江戸末期まで金桜神社は金峰山信仰の拠点として繁栄を極めていたが、明治維新の廃仏毀釈の波に襲われて、衰退の一途をたどりました。日々の生活にすら困窮するようになってしまった下級神官社家の人々は習い覚えの水晶研磨を本業とするようになり、鉱山採掘許可による原石多量化と共に水晶研磨は盛んになり、商いの便利な甲府に工場を建て、御岳から甲府へと水晶興業産地は移り、水晶原石を掘り出す人々、研磨する人々、そして商売を広げる人々と、山梨の水晶産地は形成されていきました。
05.工業製品から宝石の街へ
昭和12年、日中戦争が始まって山梨の水晶は大打撃を受けます。昭和15年のいわゆる贅沢を禁止する法律、「奢侈禁止令」で水晶製品ははずされはしたが、様々な制約を受けることになってしまいました。止むを得ず、主軸として扱っていなかった水晶の工業部品の生産に尽力せねばならなくなりました。即ち、水晶振動子・レンズ・絶縁体等の軍需研磨品の生産体制に組込まれていきました。戦後、装身具業界も急速に立ち上がります。町や、工場倉庫は焼けてしまいましたが、水晶原石は焼け跡から続々と掘り出されました。昭和21年には、首飾、イヤリング、ペンダント、指輪の芯石の生産に励み、僅かではあったが輸出も始めた。「宝石の街」へと徐々に復興していきました。